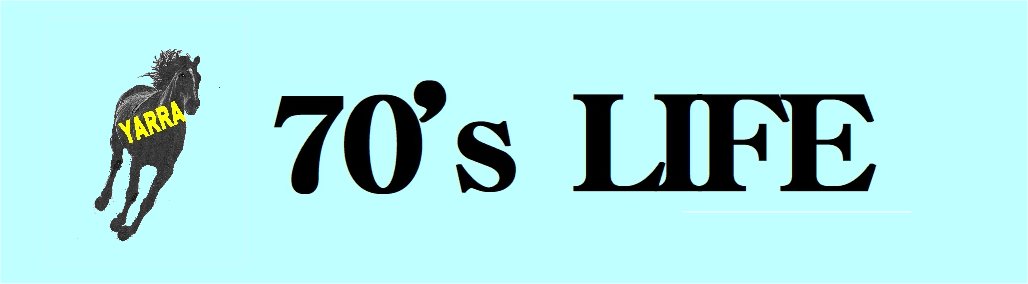2.第二審での論点(投資者保護基金の補償をどう捉えるか)
(1)裁判所側の論点
(2)弁護側の考える判決の問題点
3.最高裁上告に向けて
1.第一審を振り返って
佐藤:第一審は,敗訴になりました。ポイントをわかりやすくまとめると、どうなりますか。
木村:一つ目は、診療報酬債券が12.8%しか売れなくても、診療報酬債券は単なる社債に過ぎないのだから別にかまわない、ということです。顧客が会社にお金を預けた時点で、それ以降の使い道については責任を問われない、ということです。
二つ目は、証券会社は、集めたお金と自分の財産と分別すれば、その時点ですでに分別管理されたこととなる。その後、集めたお金を海外に移動したとしても分別管理義務違反にはならない、ということです。
リー:法律家たちの使う言葉って、難しくてわかりにくいけど、こうやって木村さんがわかりやすく話してくれたの聞くと、何それっていう感じになるわね。
キム:集めたお金を海外に移動するって、資金洗浄とかマネーロンダリングのことですよね。ネトフリで「ブレーキング・バッド」を見ました。それが分別管理義務違反にならないということですか。
木村:そうなりますね。
キム:それってなんか、変じゃありません?
木村:わたしもそう思います。
佐藤:それでは、話が広がりそうなので、その件は次回に回すこととして、第二審の様子についてお聞かせください。
木村:わかりました。 第二審は、2022年7月22日に、東京高等裁判所で行われました。しかし、結果は、やはり私たち原告側の全面敗訴の判決でした。
2.第二審での論点(投資者保護基金の補償をどう捉えるか)
(1)裁判所側の論点
裁判所の判断は、次の通りです。
①基金による補償は、あくまで金商業者による分別管理が機能しない場合における補完的な制度である。
② 補償すべきか否か、すなわち顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかの認定は、もっぱら基金に委ねられている。
③金商法上、一般顧客が基金に対して上記認定を求めたり、その判断を一般顧客が争ったりする手続は法定されておらず、同基金の認定や公告を経ずして、一般顧客が同基金に対して認定や支払を求める手続が法定されていない。
(2)弁護側の考える判決の問題点
この裁判の判断に対して、弁護側の考える判決の問題点は、次の通りです。
控訴審は、基金が補償金を支払う必要がないと判断した場合には、投資者が、その支払いを求めたり、基金の判断を争ったりする余地はないと判断しました。しかしながら、基金は、金商法に規定された一般投資者を保護するために制定された公的な制度であり、金商法自体、証券取引に対する信頼性維持を投資者保護基金制度の目的として掲げています。また、投資者は、かかる基金による補償がなされることを前提に投資判断を行なっています。
控訴審の判断は、基金自体が補償の必要がないと誤った判断をした場合であっても、投資者がその判断を争う余地が一切ないとするものであり、投資者保護基金が制定された制度趣旨に明確に反するもので、司法による救済の道を閉ざす不当な判決であることは明らかです。
また、当方が控訴審にて追加主張した点についても、控訴審は、あくまで説明義務違反の問題に過ぎないとするのみで、具体的な判断を示していません。)
ナレータ:投資者保護基金のホームページを見ると、次のような説明が書いてあります。
「投資家保護の活動のために必要とされる十分な金額は、業務規程の定めにより500億円です。投資者保護基金が500億円未満の場合、会員証券会社は1年につき50億円の算定基礎額に基づいて計算される負担金を支払う必要があります」。
しかし、第二審での裁判所の判断によりますと、基金は、会員である証券会社から会費を徴収して常時500億もプールしているのに、その基金からお金を出すかどうか、基金自身が判断し、場合によっては救済しない場合もありえる、ということになります。
キム:最後の部分、ちょっとひどくありません。500億円も常時プールしておきながら、そこから払うかどうかは基金が決めるなんて、まったく公金の私物化じゃないですか。だって、もともとは,投資家から集めたお金でしょ?
3.最高裁上告に向けて
木村:弁護団は、第一審において、基金が主張する「分別義務違反」はなかったという論点を突き崩すために、第二審までの10ヶ月間文字通り「死にもの狂い」で準備してきたのです。 しかし、第二審でも、あくまで説明義務違反の問題に過ぎないと一蹴し、具体的な判断を示さなかったわけです。
弁護団も、今回のこうした裁判所の素っ気ない対応に、さすがに危機感を覚えました。そして、「今までの弁護士生活のなかでも聞いたことがない不当な判決内容だ」といっています。
そこで、私たち原告は、直ちに最高裁上告に向けた準備を開始しました。